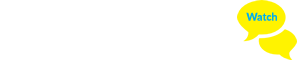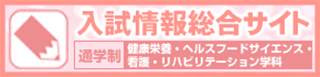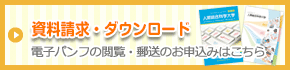人間科学部@蓮田健康栄養学科
【健康栄養学科・授業紹介】食環境生産教育実習 1日目
58 views
食環境生産教育実習(3年生配当選択科目)の一部として、10月17日(金)から18日(土)の1泊2日にて、宇都宮大学農学部附属農場の拠点事業に参加しました。
10月17日(金)10時、宇都宮駅に集合し、宇都宮大学様が用意してくださったバスに乗り、30分程かけて農場に到着。初日は講義が中心で、2日目は前日の講義を踏まえての酪農実習と牛乳の加工実習としてアイスクリームを作りました。天候にも恵まれ、有意義な実習となりました。
初日の講義は、11時から「酪農科学概論」、乳牛とのスキンシップを挟んで、「動物生殖科学概論」、「生殖科学実験」と続き、18時半まで酪農の生産から流通、消費、そして農家の現状について学習させていただきました。
宇都宮大学の長尾慶和先生にご教授いただいたのですが、先生からの質問に対し学生から珍回答が続出で、「事前学習したはずなのに・・・」と、帯同した教員は絶句してしまいました。それでも終始、和やかな雰囲気で受講させていただきました。
「酪農科学概論」では、牛乳は、本来、仔牛のためのものであり人間がそれを分けて貰っていること、卵やミルクなど人間に食べ物を提供できない動物の雄の一生は短いこと、雌であっても家畜や実験動物は、寿命を全うすることができないことなどの話を拝聴しました。学生は、改めて、「(尊い命を)いただきます」の意味を実感し、食べ物への感謝の気持ちを忘れずに過ごしたいと話してくれました。
「動物生殖科学概論と同実験」では、家畜生産の現状を学習しました。乳牛は、全て体外授精で、人間のために特化した遺伝子を残していくそうです。実験では、宇都宮大学の学生さんや大学院生さんがTAとなりサポートしてくださり、牛の卵巣から卵子を吸引採取したり、顕微授精の模擬実験などを行ったり貴重な体験をさせていただきました。
屠畜場から持ち帰った卵巣から卵子を吸引採取したのち、TAさんのサポートにより、顕微授精用に卵子を取り出している様子

顕微鏡(PC画面)を覗きながら、顕微授精(マイクロピペットを用いて1個の精子を直接卵子内へ注入し受精させる方法)の模擬体験

~*~ 講義の合間の牛とのスキンシップの様子 ~*~



乳牛とのスキンシップを終えて、「一頭、一頭性格が異なり、想像以上に感情表現が豊かな動物だと感じた」と感想を話してくれました。
初日は疲れたようで、女子は早く就寝、男子は遅くまでおしゃべりをしていたようでした。
2日目の実習については、また改めて...
(健康栄養学科 教員 鈴木恵美)
☆因みに、昨年度は夜から深夜にかけて、牛の出産を見学させていただきました。
↓その時の様子です(左が産まれたての仔牛を洗っている様子。右は産まれた仔牛)